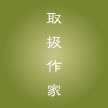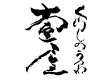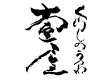実に7年ぶりの展覧会になる。今回の「折敷」という企画を浩彦さんに持ち込んだのは、確か2018年と記憶している。コロナ禍によって二度三度の会期延期を経て、ようやく陽の目を見ることになった。
壺屋の暖簾をあげて20数年。他の有名陶芸店やギャラリーほど多くの酒器や食器を扱ってきてはいないにしろ、四半世紀の間には数多くの記憶に残る作品を扱わせていただいている。あるお客様から「せっかくいい酒器に巡り合えたのに、これで一杯やるときの折敷に気に入ったものがないのよね。」の一言から始まった今企画。
山中いや日本中に轆轤の名手として不動の名声を得ている川北家に、折敷という今までの仕事とは少し違った方向性の企画。最初に浩彦さんに話を持ち込んだ時の、何とも言えない表情が忘れられない。二度三度と企画の内容を詰め、川北家が長年手間暇かけて集めた銘木での制作を依頼し、最初の日程が決まったのは確か2020年春開催。すでに横浜港での大型客船内感染の報道を経て、第一次の流行期に突入しており当然延期に。
そうこうしているうちに、某放送局の美の壺という番組で「折敷」が放映(2021年1月)され世の中の注目と反響と共に、浩彦さんにも壺屋が求めている方向性を理解していただいたようである。ところが、折敷に対する注目度と比例するかのようなコロナ禍の波は、この企画の幾度目かの延期を余儀なくさせた。
今考えると、この延期が壺屋にとっては、浩彦さんとの「折敷」というものに対するすり合わせに必要不可欠な時間であったように思う。また、この時間が浩嗣さん(子息)という新たなモノづくりの挑戦の機会となったようである。父上の良造先生にもご協力いただけるとのことで、親子三代共演が実現する実に楽しみな企画となった。時間というものの不思議、それは前を向き絶え間ない努力を惜しまないモノづくりには、必ず味方をするものだ。