 |
|||||||||||||||

六瓢
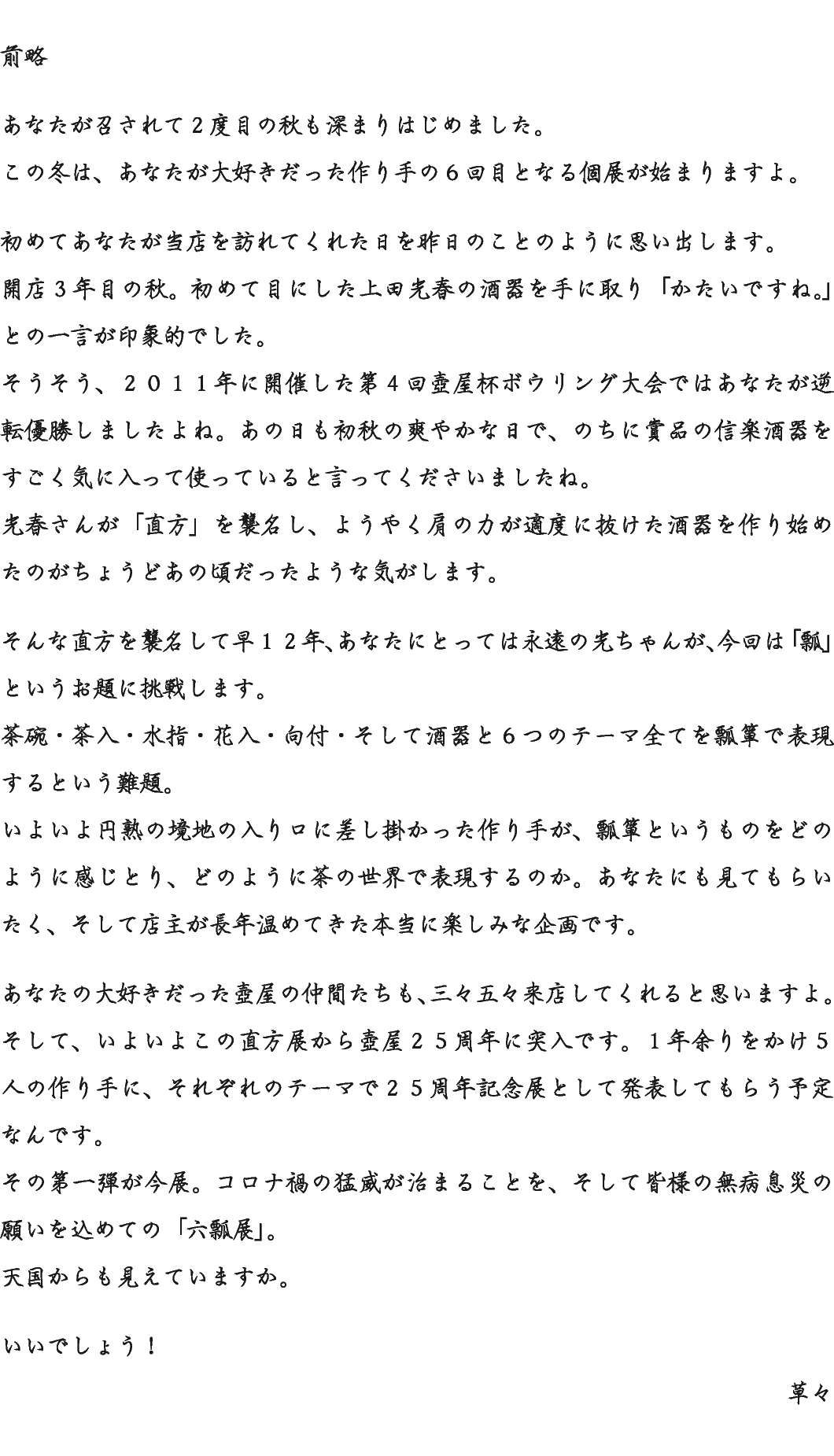
 羅漢 |
素敵な方がこの春天国へ召された。6歳上の親代わりであり唯一無二の男兄弟であった。末期がんを宣告されてから1年半余りの間に、社長業の整理移行に始まり、身辺整理から果ては己の死に装束まですべてを自身で周到に準備し、旅立つ数ヶ月前まで趣味のゴルフから奥様・家族との旅行と、思う存分生き抜いた方であった。 一方、やきものに憧れ丹波での弟子生活、捲土重来を期し陶芸家を志した信楽での修行、そして六代・直方襲名前後の苦悩の日々。すべてを実家の九州八女の地から、時に励まし時に温かく見守り応援し続けてくれた方の死をどのように受け入れ、どのように見送られたのか。店主にとっては、知る由もない。 そんな中、さらにコロナ禍の中、深い慟哭の中にいる光春さんに『羅漢さま作ってみませんか?』と声を掛けた。阿羅漢、釈迦の弟子十六羅漢さまを己が掌から生み出す過程から新たな光が射すのでは、との思いも伝えて。 返事がいただけないまま数ヶ月が過ぎたある日。『結集での五百羅漢は無理までも、納得できるまでつくってみるわぁ。』との連絡。壺屋に所狭しとお出でになる羅漢さまを想い、このコロナ禍で閉塞しきった人々のこころに少しでも寄り添って欲しいと願った。 羅漢さまづくりもひと段落。DMの撮影にと窯場を訪れると、焼成前の羅漢さまが所狭しとお出迎えくださった。慟哭の中から生まれし苦悩の羅漢さまに始まり、直前に生まれし羅漢さまは微笑みを浮かべた愛おしいお姿であった。撮影も終え、夕焼け空が美しく光りはじめた陶房で帰り支度をしていると、直方氏が『ちょっとおもろい茶碗作って持っていくわぁ』とのひと言。 そこには、深い慟哭から新たな創作への標を見つけた陶芸師の顔があった。 |
 火色 |
スイッチが入ったようである。前回の個展は、六代・直方として新たな造形の模索から生まれた「壺」での展覧で、会場を訪れた方々を大いに楽しませてくれた。 あれから丸3年。昨年各地で開催された一連の還暦展での続けざまの焼成の中からヒントを得たという、新たな「火色」を今回の展覧のテーマに据えることとなった。 六代として直方を襲名以来、ここ数年駆け足で過ごしてきた。この間に五代を見送り、自身の還暦という一つの節目を過ぎ、「六代として」の模索はいよいよその深きを求めるものとなっている。改めて上田直方としての系譜を見つめ直し、我が成すべき道を模索し、上田家伝統の信楽の火色をさらに昇華せんと考え始めていた矢先に出会った新たな「火色」。彼自身のあくなき探究心の炎が大いに燃えはじめたようである。 代々仕事を継承していくという作業。周囲の人間が考えるほど、甘い世界ではあるまい。150有余年の歴史を刻んだ「上田直方」という名跡は、簡単に語りつくせ、越えていける道のりではない。ましてや、その時代の先頭を歩んできた代々の職人技と対峙するということは、逃げ出したくなる葛藤との戦いでもある。ただ、そこから目をそむけず、真正面から取り組んだ者には、時代を超えて燦然と歴史に名を刻むという、計り知れないご褒美があるはずだ。 六代・上田直方。還暦を過ぎ、いよいよその本性を現そうとしている。果たして、その一端を今展で見せるや否や。すべては彼の作り手としての生きざまに帰結する。絶対に逃げていては見えぬ世界がそこにはある。 人が一生を賭し成し得た仕事というものには、時代の流れなどクソ喰らえである。 |
 信楽水指 |
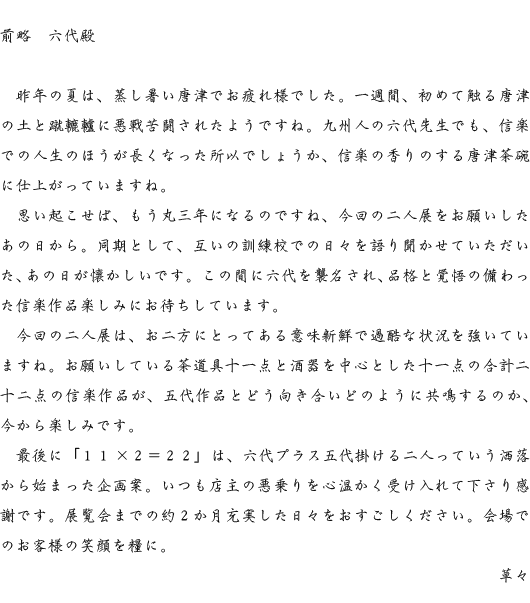

「壺屋de壺展」 |
結局、10年の歳月が流れることとなった。2014年初冬に予定していた「壺屋で壺展」は【壺屋de壺展】とタイトルをモダンに変えて、2015年新春第一弾として上田光春10年振りの個展開催の運びとなった。 十年一昔。日本人はこの言葉で、巧みに移りゆく世の中を表現してきた。確かに10年も経つと、町並みは変わり、社会情勢も大きく変化する。自然災害のような目に見えない力もあれば、経済という化け物のパワーに流されていく人の心も然りかも知れない。かく言う、上田光春氏もこの10年の間に、六代として上田直方を襲名されるに至って、その作陶環境は大きく変化した。茶陶の名門を継承し、名に恥じない作品を世に送り出すという作業は、想像以上に自身に重くのしかかり、その生み出す作品は見えざる枠に囚われざるを得ない。確かに茶陶界におけるモノづくりとして、襲名を契機に昇竜の如くステップアップをされたように思う。ただ、見えざる重石の影でその幅は、鶴翼の如くと言い切れるだろうか。 上田氏が持ち込んだ企画「壺屋で壺展」を、店主が勝手に【壺屋de壺展】とタイトルを変えるに至った経緯は、実は少なからずこの見えざる10年に帰結する。この10年で茶陶界は、大きく変化してきている。詳しくはまた別の機会に譲るとして、国際的に通用する茶の文化の構築とそれに伴うモノづくりの努力と成長なくして、今後を語るなかれと感じている。そして、個展タイトルの小さな変化を敏感に感じとり、展覧会開催の順延を決めてまで、新たな作品に取組むモノづくりとしての姿勢を目の当たりにしたとき、鶴が大空へ羽ばたく美しい姿を見せてくれることを、大いに期待している。 十年一昔。人の心は移ろいゆくのではなく、成長を見守り続けている人々の存在を感じる展覧会にしたいと願っている。 |
 信楽壺 |
襲名から3年、ようやく心に少し「ゆとり」の3文字が彼・六代上田直方から漂い始めたと私には感じる。有難いことに彼とは壺屋開店以来この15年、陶芸家とギャラリーとしての関係は基より、個人的にも弟のように可愛がっていただいてきた。 ギャラリーとしては、数々のとんでもない企画を受けていただいた。初開催の二人展では即興でのギターの生演奏が飛び出し、当店での初個展では3週連続3企画の展覧会を、2回目の個展では窯の築窯からその窯での初めての作品のみでの個展を開催した。その後の二人展を中心とした幾度かの企画展では、萩焼や丹波焼などの作品も作っていただいた。 個人的には、盃を傾けるだけではなく、ボウリングや、今では年一回恒例となった魚釣りまでご一緒させていただいている。15年の歳月は、互いの顔に年輪を刻ませ髪にはたっぷりと雪を被らせている。 そんな彼が、昨年末久しぶりに大壺を焼いた。窯焚きの最中、差し入れをもって慰問に訪れると、ふっと一言「壺屋で何年個展していない?」と尋ねるので、「丸7年。」と答えた。「壺屋で壺展やろうか?」に「洒落ですか?」と返すと、窯焚きを手伝うKくんと三人顔を見合わせて爆笑に包まれた。 その時の壺が、今回掲載の大壺である。大らかでのびのびとした造形がそこにはあり、穴窯独特の灰の景色が壺全体の雰囲気をさらに包み込むような「ゆとり」を醸し出している。 『壺屋で壺展』。壺屋始まって以来、初めての作り手の発案企画である。来年(2014年後半開催予定)9年振りとなる上田光春というものづくりの個展。六代直方としての責任と覚悟を内に秘め歩み始めた彼が、壺という宇宙にどんな星座を描き、どんな内面の成長を見せてくれるのか。今から待ち遠しい企画である。 |
|
信楽からようやく茶碗が届いた。 上田光春としての35年の陶歴に新たに書き加えられた六代直方の一行。 ここ数年で刻まれた皺そして増えた白髪。 六代襲名までの道程を感じる。 今は多くを語るまい。 作品がすべてを語っているのだから。 |
|
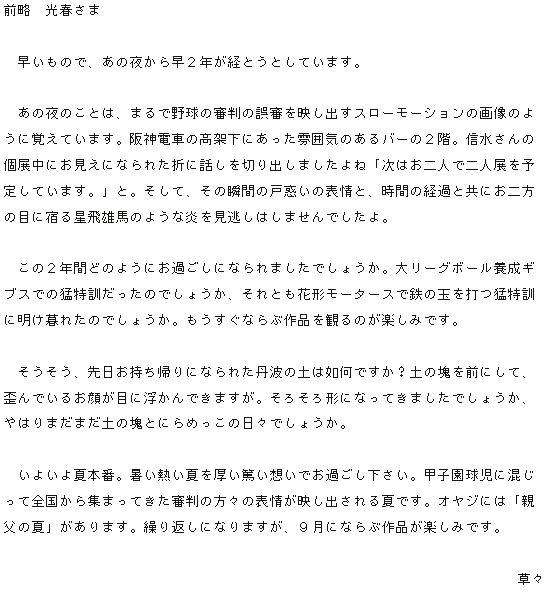
|
秋の訪れが秋分を跨ぎ、春の芽吹きが春分を待てなくなって久しい酒蔵の町で、彼の片口が麹の発酵する匂いを楽しませてくれた次の朝、昨夜浮かんだあるひとことがこころの隅から拡がり目が覚めた。 「不易流行」。不易を知らざれば基立ちがたく、流行を知らざれば風新たならず。もう少し砕いた言い回しをすれば、不変の真理を知らなければ基礎が確立せず、変化を知らなければ新たな進展がない。松尾芭蕉が体得した俳諧の概念であるにもかかわらず、現在社会においては企業価値観構築から人間形成の一助としてもひろまっている。 上田光春という陶芸家。本人は陶芸師とおっしゃる。彼と深く付き合えば付き合うほど「不易」に関する真理を追究しているものづくりであると感じる。「家」をかまえず、プロの技術者としての「師」を旨とする。人としての成長を求め、自らの内なる変化を待ち、それを形として搾り出したところに今までの彼のうつわの中心がある。「流行」という概念で彼のうつわを捉えた時、自らが求める変化を外に求めることで、さらなる加速を促す要素が見え隠れしているように思う。 つまり「不易流行」のもう一方の真理であるところの「不易と流行の一致」。すなわち「不易」は「流行」の中にあり「流行」が「不易」を生み出すという概念。このことに対して彼がもう一歩踏み出せば・・・、真理が鮮明に見えてくるように感じる。 立冬に咲き始めた、季節外れの秋桜(コスモス)を片口に挿してみると、昨夜の麹の香りが消え、光の春を運んで来るように。 |
|
もうひとりの九州男児が腰を上げた。 新しい窯作りも、ようやく基礎部分を終えレンガ積みという重要な部分にさしかかっている。 そんな時、手弁当で一人の陶芸家がやってきた。萩焼の吉野桃李である。 二人を引き合わせてから、かれこれ3年。いい関係である。今年4月の吉野桃李展の折り、信楽での窯作りの話を彼に持ちかけると二つ返事で『手伝いに行きますよ。』と快諾を得ていた。 カレンダーの裏に書かれた怪しい設計図をもとにふたりで築窯に取り組む姿を目の当たりにしたとき、ひとつの時代のうねりを感じずにはおれない。 今回の窯は、連房式穴窯とでも命名したくなるような代物である。従来の穴窯に見られる焚き口と焼成室が一体となった炎形の部屋の後ろに、もう一室片方から横焚きをする焼成室を設け、その後ろに小さな捨て間そして煙道につながるという構造である。そして、もうひとつの特徴は、窯の急勾配と「半地下式」をはるかに超えた「ほぼ地下式」の構造にある。 ねらいを聞くと、焚き口での思い切った窯変作品の焼成と、次の間でのまったりとした火色作品の焼成という。従来の彼の穴窯では、燃焼室イコール焼成室という構造から窯変と火色という相反する作品の焼成は困難を極めた。また加えて、今回の急勾配とほぼ地下式の構造が及ぼす影響を鑑みたとき、出来あがってくる作品に新たな息吹を感じずにはおれない。 『挑戦』と位置づけた年末(2005年)の上田光春展。窯作りのエネルギーから生まれる新たな作品に対する彼の挑戦は、陶芸界にとって初の試みであろう大晦日(個展最終日)深夜までの営業という壺屋の『挑戦』を誘発し、幕を開けようとしている。 |
|
九州男児がようやく重い腰を上げた。 前回の個展(2003年)では上田光春というものづくりの本質に触れる展覧会を開催できたと思う。3日間3テーマ3週連続という展覧会は、過酷でもあり充実したものでもあった。展覧会の活気と作品から発するエネルギーは予想をはるかに超え、彼自身のもつポテンシャルを最大限引き出せたのではないかと満足している。 そして、この冬には彼の2回目の個展を予定している。もちろん、前回と同じような展覧会を催す考えは展覧会翌日からない。そして新たな企画をこの1年半、事あるごとに彼とは論議してきた。そんなある日、彼にひとつの提案を試みた。『次の壺屋での個展は、新しい窯でしてもらえませんか。』と。 新しい窯イコールいい作品などという夢物語を企画して言い出したのではない。また、初窯展でお客様を呼ぼうなどという姑息な考えから生まれた企画でもない。 今の穴窯の数十メートル山裾に、10年近くその窯は焚かれることなくひっそりと佇んでいた。直炎式のオーソドックスな穴窯。5代直方氏と若き日の彼がその窯で何を語り何をぶつけあってきたのか。そんな若き日の思いが一杯詰まった窯は、その思い出と共に新しい窯材として再利用する計画であるという。 そして、今回の窯の解体作業には一人の助っ人がいる。彼の弟子である。非常に寡黙で真面目な好青年は、黙々と窯の解体作業を師匠と共に進めていると聞く。普段から指示された仕事をコツコツとこなすこの青年を見ていると、今回の作業の順調さが手に取るように伝わってくる。そして、築窯にはさらに一人助っ人がやって来る予定であると聞く。 今回の初窯展は『挑戦』と位置づけている。まったく新しい窯で作品を焼く上田光春という陶芸家の挑戦。窯を解体し築窯するという、願っても体験できない経験から何を学ぶかを問われている弟子の挑戦。築窯に駆けつける助っ人の人生を含めた新たな挑戦。 そして、彼らに『挑戦』を求めるからには、壺屋も今までどの画廊も企画したことがないであろうことに『挑戦』する。今この原稿を書き終えて『挑戦とは過去の経験の上に構築された破壊である。』というある哲学者の言葉が脳裏を掠めた。 |
|
いよいよ練りに練った展覧会が始まる。 壺屋が産声を上げて丸5年、様々な出会いを経験した。そんな中でも、上田光春というものづくりと出会えたことは壺屋にとって格別な意味を感じる。 過去に『主人蘊蓄』のページで、『ギャラリー』の概念を「天井桟敷」でありたいと書いたことがある。作り手が最新作を持ち込むだけの展示室としてのギャラリーのあり方に疑問を持ち、自身で始めた壺屋。形だけの企画展やコラボレーションなどと銘打った貴方任せの展覧会が溢れている昨今である。本当に作り手の懐に飛び込み、作り手の『現在』を見つめ、『未来』を引き出す企画を練り、発表するステージを提供する。そしてそのステージが一番よく見えるところが「天井桟敷」であると考えている。 まだまだ大きな舞台を提供できる力もなければ、たった5年で作り手の懐深くに飛び込める訳もない。ただ、今回の上田光春展は、彼との『縁(えにし)』を大きく膨らませた企画を用意出来たと思う。人が集い、笑顔が溢れ、熱気に包まれ、出会いが生まれる。すべては彼の作り出す作品がその答を持っている。 今回掲載の三作品は、上田氏とカメラマンの中島繁樹氏との『縁』から生まれた絵である。ここにもひとり天井桟敷の住人がいる。 |
|
あの暑い夏の日から1年。片鱗があらわれた。 陽炎の向こうの白鷺城を借景に満面の微笑みの記念写真。姫路市立美術館での2002年夏の思い出深い一日は始まった。『桃山陶芸と魯山人』展。彼が東北での自身の個展の帰りに、どうしてもと立ち寄った展覧会である。会場に入った時、互いの微笑みは消え、言葉を失い、桃山陶の名品の数々に魅せられた。数時間後、会場をあとにするとき夕日に照らされ一瞬あらわれた彼のあの厳しい表情が忘れられなかった。 そして晩秋の信楽。いつも作品を乾燥させる棚に、無造作に置かれた花入があった。「あぁ、あれ。窯に入れるの忘れてんねん。」と口にする瞬間の彼の表情が、あの日の表情であることに気づいた。「太郎庵?」との問いかけには、もういつもの微笑みを返す彼しかそこにはいなかった。 それから半年。壺屋での今冬の個展用作品のためのロッカーに無造作にその花入は置かれていた。 「焼けすぎかな?火前で思いっきり虐めてみたんよ。くたばれへんかったな。生命力があるわ。」出番を待つ秘蔵作品の中に、ひときわ堂々と佇む花入であった。 あの夏に見た桃山の備前双耳花入『太郎庵』。只の写しではない、彼が思いえがく僧侶の姿がそこには映し出されていた。いや、それは彼自身の姿なのかもしれない。 |
|
ひとことで言えば、縁の深い陶芸家である。最近、彼の秘密のホームページ日記にも、ちょくちょく登場させていただいている。また、彼とのメールのやり取りも200通を越えた。しかし、取り扱った彼の作品は、壺屋で開店当初から常設させていただいている作家の中で一番少ない。これが、彼との関係である。 ゆっくりと水をくぐらせしっとりとした火色の魅力は、古備前のそれとの比較においても引けを取らない。そんな「矢筈口水指」があがってきた。2001年11月開催の丹波茶陶界の鬼才・北村圭泉との2人展に向けて、送り込んできた作品である。 今度の2人展を十二分に把握している彼は、今まで以上に作品を厳選してくるであろう。当然そこには、奇を衒う作品も、自分にない作品も、北村氏に対する作品も、存在しない。そう思わせる出来の「矢筈口」である。 今後とも、彼とはゆっくりと縁を深めていきたい。彼の持っている、茶陶・信楽像は確かなものである。そして何より、加速する作陶活動の中で、確実に光春信楽を作り出し始めている。これは六代目直方を義務付けられた宿命に対する、アンチテーゼではなく、受け入れ昇華させようとするパワーがもたらすものに他ならない。 今回の2人展の主題は、すでにおふたりには伝えてある「第一回ですよ!」と。 |
|
9月中旬の深夜。いつものようにメールチェックをしていると、受信ボックスに見慣れたアドレスからメールが一通
。「壺、出ましたヨ!」。待ちに待ったメールである。 急ぎ日程を調節し、一升瓶を片手にイザ信楽。家人の留守をいいことに泊まりがけの直談判。昨年のちょうど同じ時期に扱って以来、お客様から催促されること数知れず、「上田さんの壺が忘れられない。」の大合唱。当然、期待も大きく、昨年以上の『信楽壺』を求める贔屓引き倒し気味のお客様方。そのことを十分承知の上で届いた一通のメール。期待と不安の緊張を隠すため、ワザと作品も見ずに夜中までバカ話に興じる。数時間の仮眠の後、やはり秋を感じさせる早朝の信楽、凛と澄んだ空気の中でいよいよご対面である。「今回の窯は、灰を出来るだけ暴れさせたんですよ。」と昨年以上にハードな『窯焚の業』に挑んでいる信楽の雄の弁。 一目見て思った、「兄弟だ」と。昨年の壺が兄貴、静かで品よく優等生であるのに芯がしっかりしている。そして今年の壺は弟、一見荒々しく粗暴に見えるが、豊かな感性と高い芸術性が見え隠れしている。 これが、1年をかけて彼が私に出した答えである。今更ながらに、上田光春という人物の底知れぬ魅力に、心の底から惚れ直している。 |
|
現在の信楽焼において、まっすぐに茶の世界と向かい合っている次世代を担える作家といえば、上田光春をおいて私は他に思いつかない。名工・5代目上田直方の後継者という立場に奢ることなく、真摯な作陶姿勢から生まれるその作品は、実に静かで上品である。これは彼の、機を衒うことをよしとしない、階段を一歩一歩上がろうとする考え方によるものであろう。 今回掲載の花入は、彼にとっても私にとっても思い入れの多い作品である。昨年(1999年)、彼はメインにしている窖窯(アナガマ)を8回焚いた。彼の窯は、約4日前後焚き続ける、それを昨年はなんと8回も焚いた。私は彼がぶっ壊れるのではないかと内心ハラハラしていた。なんとその結末は、昨年末に窯がブッコワレタのである。彼は平然と「こんどの新しい窖窯は、楽しみですよ。」と昨年末言い放っていた。そして上がってきた作品が、この花入である。 一目見た時、私は言葉を失った。窯の焚口近くの火前に置かれ(大壺2点とこの花入の3点のみが、初窯の火前の栄誉を得た)、熾き(オキ)に埋もれ焦げが半面を覆い、斜めに埋もれたことによりビードロが高台にまで廻り込み、玉垂れが程よくみられ、幾筋かは蜻蛉の目になっている。彼が今一番大事にしている「火色」の景色もしっかりと顔を出している。 これまでの彼の作品を一回り大きくしたように私には映った。いままで私は、彼の「静」の作品に魅せられてきた。この作品は、彼の内なる「動」が見事に具体的に表現され、新たな魅力をみせている。 くしくも、窯出しで彼が残している写真の中に、唯一単独で撮ってあったのが、この作品である。この時私は、彼のこの作品に対する思い入れと私の感じたものが、無言の言葉となって交わされたのを感じた。 今、店でこの花入を前にし、彼の帰り際に言っていた言葉がよみがえってきた。 「今度の窖窯、4回目の窯出しを楽しみにしてて下さいよ。」 いったい彼は何者なのだろう。 |
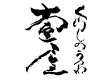
※ 当サイトに掲載の写真・テキスト等の無断転載を禁じます。









