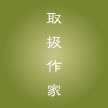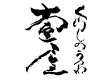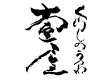まさかこんな早くに、という思いでこの項を書いている。
今年初めに彗星の如く現れた「田上笑」というものづくり。久しぶりに彼女と話をしていると、店主が忘れかけている何かを思い出させ、気づかさせてくれる。黙々と江戸時代の浮世絵と対峙し、絵師としての感性を磨き、刃物を研ぎ、山桜の版木に彫り、稀少な竹の皮を編んで作られた本ばれんで、越前の手漉き和紙に摺る。時として一つの作品の版木は10版以上、時には15版を超えることもあるという。そんな、ものづくりとしての修練の日々が、彼女の成長を促したのだと感じる。
前稿でも少し触れたが、田上笑が技術を学んだ立原位貫氏という木版師。面識はないが、調べれば調べるほど彼の歩んだ道は壺屋が歩み始める上で指標となった陶芸家・西岡小十氏の歩みに重なる。独学でその世界に飛び込み、人と出会い、踠き苦しみ、再び自分を見つめ、道半ばでこの世を去った。立原氏から、彼女は自分の知らないうちに多くのことを学び、多くのことを託されている。また折に触れそんなエピソードも披露することもあろうかとは思うが、まずは彼女が浮世絵にかける想いを紡いだ一文を紹介する。『私は自分の作品を見てくださる人たちに、日本人の心の源流にある大自然(神仏)や生きとし生けるものへの眼差しを、もう一度全身から思い出し沸き立つことを感じてもらえるような、、、そんな作品を作り上げることが夢です。』と。
2026年1月に彼女のデビュー展開催用にと送ってきた画像が、歌川国芳《猫の当て字 河豚(ふぐ)》〈復刻〉だ。原画の生き生きとした猫の表情とフグの動きが、見事に表現されている。また加えて、彼女から新春の今展にとひとつの提案があった。歌川国芳の「よきことを菊の十二支」という作品の「午」を写した小品を発表するという。以降順次、その菊の十二支を発表しようという彼女の意気込みを聞かされると、壺屋開廊29年目の春に40周年の光が遥か彼方に灯されたような気がする。 |