 |
|||||||||||||||
|
日本の箸文化を紐解くと、聖徳太子から遣隋使にまで遡り、箸置きも同時代の神前儀式に用いられた耳土器(みみかわらけ)が始まりといわれています。ただ、発展の歴史は大いに異なり、箸文化は衛生面からもその時代から庶民にまで広まったものの、箸置きは江戸後期から明治に入ってようやく広まりはじめた文化のようです。どちらにしろ、箸のみで食する日本特有の食習慣が、今日の箸置きの百花繚乱を生む素性にあったのは紛れもない事実のようです。 古き時代に作例がなく、またこの時代にはなかなか折敷に合う小粋な箸置きにも出会えないと嘆くお客様から「箸置きを作ってくれる作家さんはおられませんか?」とのお声がけ。ここは苦労に苦労を重ねて秋刀魚長方皿の企画を見事に昇華させた眞清水さんしかいないと白羽の矢で頼むことしきり。何とか口説き落としての今回の企画となった次第です。 さて、と制作に取り組み始めたまではよかったものの、いざあの小宇宙に様々な釉薬をかけての試作の段階で、数々の難問が噴出したようです。長方皿とは全く違う、ちいさきやきものに宿る美の世界観。1年以上に及ぶ孤軍奮闘から十種類以上の箸置きを生んでくれている様子。さらに、家人からの西洋料理を中心に用いられるカトラリーレストの依頼にも真摯に答えを出してくれたようです。 五代・眞清水藏六というものづくり、高校時代はラクビー部のキャプテンまで務め上げた好漢。何事にでも真正面から取り組むその姿勢は、ものづくりの資質としては何ものにも代えがたく、還暦目前にしてその努力は山溜穿石の如くに感じます。 令和4年がどんな年になるのかわかりませんが、新春を飾るに相応しい茶道具の逸品も同時にならぶ、華やかな企画から幕を開けます。 |
|
二度の会期の延期を経て、ようやく陽の目を見ることになった。あるお客様から「秋刀魚を丸ごと一匹乗せられる皿はないですかね?」の一言から始まった企画である。 近年の不漁により高級魚の仲間入りかと、云々されている秋刀魚。確かに丸々と太った秋刀魚を炭火で焼いて食するのは、日本人としての秋の楽しみの一つであった。そして近年の不漁と相前後するかのように、世の中から秋刀魚を丸ごと一匹乗せられるサイズの長方皿も姿を消したように感じていたのは店主だけではなかったようである。 この話をいただいてから、店主は店主なりに思いを巡らしてみた。サイズ、色調(釉調)、作り手(作家)等々、やはりこれは眞清水藏六に持ち込む以外にないと心に決めて依頼した次第。もちろん、サイズや釉調は一切お任せで「個展として成立させたい」との一言を添えた。 西岡小十氏の元で十年間修業を積んできた経歴は伊達ではなかったと感じさせる、店主が思い描いていた以上の作品が仕上がってきた。長さ38センチ幅13センチを超える見事な唐津焼の長方皿。昨今の秋刀魚皿というとせいぜい30センチ、立派な秋刀魚は斜めに置かざるを得ないサイズである。いろいろ調べてみると、これも昨今のキッチンや収納棚事情に始まり、果ては秋刀魚を半分に切って食す習慣にまで行き当たった。 昭和の時代が限りなく遠く感じる今日この頃。たっぷり脂の乗った秋刀魚をとっておきの唐津の長方皿で食す風景は、昭和の庶民にはどう映るのであろうか。令和の時代に、ひと窯で取れても4点という長方皿を、当初元年秋に予定していた会期を二度延長してでも、そのサイズを頑なに譲らず仕上げてくる作り手の「秋刀魚の季節過ぎちゃいましたね」の一言とその写真に、来年の秋の豊漁を祈らずにはいられない。 |
|
五代・藏六を襲名して早や4年。各地での一連の襲名展がひと段落し、ようやくじっくりと腰を落ち着けての作陶機会が訪れた。前回の壺屋での個展は、襲名直前の本名・徹として最後を飾るに相応しい内容の展覧に、訪れた方々の熱気と作家本人の手応え十二分の作品が呼応し、9日間の会期があっという間に過ぎたのを、昨日のように思い出す。 襲名後、壺屋で初めての五代・眞清水藏六展(2017年10月開催)は「叩き」というテーマを中心とした展覧で、と前々から彼にはお願いしていた。唐津の土の特性もあり、ある程度の大きさの作品を作る時には、「叩き」という技法が唐津焼のひとつのワザとなっている。ただ、叩きを中心にとなると、その作陶には時間と手間を要すため、前回の展覧会から丸4年半の月日が流れることとなってしまった。 今回掲載の彫唐津茶盌も、叩きの技法を取り入れた新しい取り組みで作陶された茶盌である。彫の力強さと梅花皮(かいらぎ)の大胆な表現が、窯変による片身替りの景色と相まって、非常にバランスよく仕上がっている。 彼とは、ここ数年、陶芸論を戦わせたり、たまには酒席での話に興じたりなど、大変身近で接しさせてもらっている。陶芸家として、ひとまわりもふたまわりも大きくなっているように私には映る。4年半の歳月が作品にどう影響し、どのような表現を今展で見せてくれるのか。 作品の後方に見える薪がなくなる頃には、きっとその答えが出ているのであろう。 |

朝鮮唐津茄子茶入
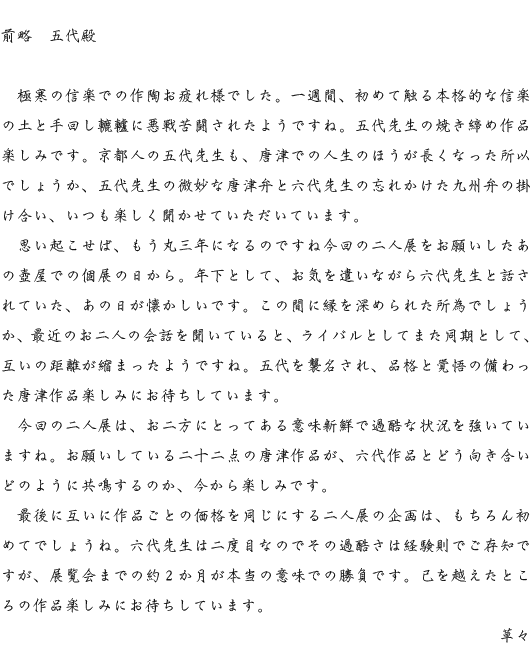
|
「割高台茶盌」といえば、古田織部所持といわれている畠山記念館所蔵の高麗茶碗があまりにも有名である。織部灯篭(この灯篭に関しては古田織部ではなく、本郷織部に由来するという説も有力である)や、この割高台茶碗の存在が、古田織部のキリシタン大名説の裏付けのひとつとされており、実にロマンあふれる茶碗でもある。その割高台は、一般的な古萩に見られるようなそれに比べ、明らかにキリスト教のカリス(聖杯)と呼ばれる盃に近い存在として語られ、確かにギリシャ十字を彷彿とさせる。これ以上この茶碗や古田織部のキリシタン大名説を論じることは控えさせていただくが、織部が生きた時代の息吹と、その後に続く日本注文といわれる名碗が数多く伝わる後期高麗ものの変遷は、非常に興味深い。 初代が窯を開いてから約200年、初代は裏千家玄々斎に可愛がられ、二代は小山冨士夫がその門を叩き、三代は石黒宗麿と入魂であったと聞く、そして先代は京焼はいうに及ばず高麗ものにも定評のある作り手である。眞清水家のやきものは、当初五条坂に窯を構えたことから、京焼を中心にその歴史を綴ってきたと思われている節があるが、歴史を紐解くと高麗ものとの関わりも非常に深い。 さて、時代は下って2013年。五代目として眞清水藏六を襲名するに至った眞清水徹というものづくりが、その襲名記念展を控え、何を考え、何を作ってくるのか、大変楽しみであった。唐津の名手・西岡小十に学び高麗ものをこよなく好む彼の手から、五代としてまず生み出されてきた茶盌が、今回掲載の独特の高台が切られた斑の割高台茶盌である。前にも触れたが、彼の作り出す茶盌には、そこはかとなく雅な匂いがした。それを、高麗ものの中でも、あえて一般的な高台からすると破調でもある十字の割高台で自己を表現しようと試みてきたところに、彼の不退転の覚悟が集約されているように私には感じる。 昨今、織部ブームが再来してきているといわれている。また、織部焼をもって「不易流行」の象徴と捉える御仁もいる。時代の流行を敏感に捉え、西の文化を見事に茶の湯に映してみせた「織部」という時代とブランド。五代眞清水藏六という作り手が、高麗ものの美をどのように捉え、咀嚼し、己の技量をもって平成という時代に花開かせるのか。興味は尽きない。 |
|
2013年1月に壺屋で、最初で最後となる「眞清水徹展」を開催する。 人と人の縁とはまことに不思議で、また深いものである。前にも触れたが、眞清水徹という陶芸家とは20年以上前に知り合い、近くて遠い存在として一定の距離で接してきた。それが、数年前から縁を深め合え、切磋琢磨しあえる仲として共に歩み始めると、彼のやきものに対する考え方が明確に見えてきて、その作陶姿勢が実に実直で澄んでいることが伝わってきた。そして共に歩み始めた頃から、彼の生み出すうつわ自体が大きく変わり始めたと感じている。 代々続く名跡を継承するということ。これは、周りの人間が思っている以上に容易いことではないようである。歴代の作品もしくは芸あるいは評価は、一番身近な比較対象であり、そして存在でもある。また、他人の評価云々ではなく、自己がまず真正面からとらえなければならない存在であり、目標でもある。そして、そのことを真正面からとらえられる人間こそが、継承出来うるのではないのだろうかと彼の最近の作品を見ていると感じる。 今回掲載の絵唐津茶盌。どこか京焼の筒茶碗にみられる上品な造形の香りがそこはかとなく漂う、にもかかわらず梅花皮(かいらぎ)と唐津独特の土味が碗全体の印象を引き締め、洒脱な筆致の絵がさらにこの茶盌に趣をあたえている。現代唐津の中心的な造形とは明らかに一線を引くその碗から醸し出される雰囲気は、五代として眞清水藏六の名跡を継ぐ覚悟と責任が見事に表現されているように私には映る。 彼・眞清水徹が本名としての最後の年に開催する本展。2013年秋の五代眞清水藏六襲名を控えたこの時期に、何を考え何を発表するのか。彼自身が「本名・眞清水徹としての集大成」と位置づけた本展に賭ける思いが宿った作品が、2013年新春の壺屋を飾る。本当に楽しみだ。 |
|
「亀が六を蔵する如く」我欲を謹む意を持つ仏典。 眞清水家にとって亀との縁は、初代に遡る。幕末明治期にのちの初代藏六氏が陶家和気亀亭に入門、天保14年に五条坂で独立開窯、名を藏六と改めのちに妙法院宮より眞清水の姓を受けるとある。 当代で四代、連綿と続く京焼名家の長男にあって唐津焼に取り組む彼が、今までの蛇蝎(だかつ)唐津といわれる釉薬技法に独自の味付けをした釉調に、大徳寺塔頭黄梅院住職小林太玄和尚が「亀遊(きゆう)唐津」と名付けたと聞く。釉調から受ける印象は、蛇蝎の一見荒々しく蛇の皮の如くのそれとは異なり、実に優美で清々しくのんびりと亀が甲羅干しをしているようにうつる。そしてその造形を、亀が六(頭尾手足)を蔵(かく)しているが如くの沓形に見立てて仕上げているあたりは、実に洒脱で愉快である。 孔子曰く「50にして天命を知る」。いよいよその作陶に磨きのかかる年齢に差し掛かった彼が、亀が遊ぶが如くの心境に至り、自らの六根(眼耳鼻舌身そして意の欲)を蔵(かく)せば、その天命はくだり、道は自ずと開けるであろう。これからが実に楽しみなものづくりであり、そしてこころのこもった洒落た茶碗である。 |
|
この秋(2011年)から、唐津の眞清水徹作品が仲間入りした。彼とは不思議な縁で繋がってきた。初めて出会ったのは20数年前、西岡小十氏の窯場である。彼が、京都の訓練校を経て小十氏の許での弟子生活を始めた頃と記憶する。その後、彼が当店を訪れる機会もあり、今考えると彼との距離は徐々に縮まっていたようにも思う。 今年の春に彼の窯である玄々窯を訪問した。通された展示室から見える景色は圧巻で、唐津湾から玄界灘まで一望でき、高島・神集島をも一枚のガラス越しに見渡せる景勝地にその窯場は存在した。旧知の間柄、そして関西人同士、打解けあうのに長い時間を要しなかった。 幕末明治期から続く京焼の名門・眞清水家四代藏六氏の長男に生まれ育ち、唐津で本物のやきものやと出会い、人の縁を大切にし、唐津の地に骨を埋めようとしている気概。元来シャイで物静かな彼が、京都の地で京唐津というやきものを選択しなかった理由を語ることはなかったが、そこには徹底的に自分のやきものを追及しようとする姿勢と、四代に渡り連綿と続く何かを打ち破ろうとする気迫を感じた。 今回掲載の朝鮮唐津徳利。造形だけ見ると備前によくみる船徳利を一回り小さく仕上げた作品である。この形に朝鮮唐津の釉薬を品よく馴染ませ、3合入るお預け徳利に仕上げている。その研究と取り組みに、彼が本質的に持っている品の良さが上手くマッチし、今までの唐津焼にない新たな風を吹き込んだ逸品となった。京唐津にはない力強さに、内包する京生まれの上品さ、彼の作品には唐津京とも呼びたくなる雰囲気を感じる。 新たに壺屋の仲間に加わった眞清水徹というものづくり。徹頭徹尾しっかり自分の歩幅で自身の道を歩むのであろう。そして一緒に歩みたいと思わせる「ほんまもん」を感じている。 |
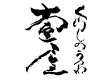
※ 当サイトに掲載の写真・テキスト等の無断転載を禁じます。






